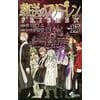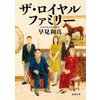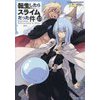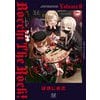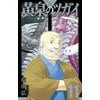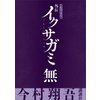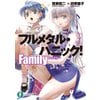要旨(「BOOK」データベースより)
これからのデジタル技術と人文学の新たな関係のために押さえておきたい思想と技術。
目次
凡例
序文─本書が目指すもの●小風尚樹・永﨑研宣
1.本書の背景/2.西洋世界のDHを知る困難の前に/3.本書の構成/4.本書が目指すもの
第1部 テーマから知る
序 テーマから知る●小風尚樹
1.デジタル・ヒューマニティーズ(DH)とは何か/2.「協働」の裏にある弱点/3.学界動向を読む/4.分野の違う他者とのコミュニケーション
1 【哲学】
デジタル・ヒューマニティーズの哲学●Neil Fraistat
1.デジタル人文学の領域/2.デジタル人文学の戦略/3.デジタル人文学のダークサイド/4.『デジタル人文学宣言2.0』/5.デジタル人文学の可能性/6.デジタル人文学の社会参加/7.デジタル人文学と公衆/8.デジタル人文学の未来
2 【人文学の危機】
人文学の危機に組織的に抵抗するDH―研究者による人文学アドヴォカシープロジェクト 4Humanities―●菊池信彦
1.人文学の危機は日本だけではない/2.「危機」への組織的な抵抗─4Humanities/3.その情報発信方法
3 【社会的責任】
デジタル時代における人文学者の社会的責任―前編―●横山説子
1.はじめに/2.McPhersonの仮説と警鐘/3.デジタル人文学のサイロ化/4.学問界のサイロ化と盲点
4 【社会的責任】
デジタル時代における人文学者の社会的責任―後編―●横山説子
1.デジタル技術とブラックボックス社会/2.デジタル時代における人文学者の社会的責任
5 【デジタル人文学を巡る議論】
イベントレポート MLA2014覚え書き●Alex Gil
1.到着/2.1月10日(金):表層的読み:デジタルのかなたに/3.1月11日(土):DHを評価する/4.1月12日(日):DHポストコロニアリズム;批判的モノ作り/5.遠くからの考察
6 【デジタル・ヒストリー】
イベントレポート 第132回アメリカ歴史学協会年次国際大会●小風尚樹
1.[Getting Started in Digital History Workshop]/2.[Facilitating Global Historical Research on the Semantic Web: MEDEA]/3.[Primary Sources and the Historical Profession in the Age of Text Search Part 3: Digital Texts and the Future of Digital History: Challenges, Opportunities, and Experimentation in Digital Documentary Editing]/4.[History from below in 3D: Digital Approaches to the History of Carceral Institutions]
7 【オープンデータ】
膨大な芸術作品を探索するためのオープンなメタデータの活用―OMNIAというWebサイト―●Niall O’Leary
1.ヨーロピアナという膨大な資源のデータ価値/2.OpenSearch APIを使ったOMNIAの開発/3.ヨーロピアナのデータを簡単にナビゲートできるようにする/4.視覚的なアプローチ/5.さらなる情報をユーザに提供するために/6.開発で明らかになった三つの問題点
8 【データ構造化】
書簡資料のデータ構造化と共有に関する国際的な研究動向―TEI2018 書簡資料 WS を通じて―●小風尚樹
1.タグセット開発の経緯とタグの解説(1-1.先行事例/1-2. の開発に向けて/1-3.タグセットの解説)/2.書簡メタデータをめぐるデジタル・エコシステム/3.CMIF の機械的生成のためのツール/4.おわりに
9 【研究評価】
デジタル博士論文のガイドライン―ジョージ・メイソン大学歴史学・美術史学研究科が発表―●菊池信彦
1.「デジタル歴史叙述」が想定された博士論文ガイドライン/2.ガイドラインの概略/3.ガイドラインの意義
10 【データベースのビジネスプラン】
Europeana の変革●西川 開
1.公的助成の減額/2.ビジネスモデルの転換:ポータルからプラットフォームへ/3.ピラミッドからネットワークへ/4.プラットフォーム期の統治構造/5.コモンズ原則/6.持続可能性を目指して
11 【データベースの評価】
「デジタルアーカイブ」の価値を測る―Europeana における「インパクト評価」の現状―●西川 開
1.はじめに/2.インパクト評価とフレームワーク/3.BVIMの重要概念/4.プレイブックの重要概念/5.有効性の検証/6.ミュージアムから見た「デジタルアーカイブ」の価値/7.おわりに
12 【教育と教育組織】
イベントレポート TEI の教育―訓練からアカデミックなカリキュラムへ―●James Cummings
1.TEIの授業として成功とは何か/2.学部レベルと修士レベル/3.入門的なTEIワークショップ/4.ツールと概念/5.教育の基礎を共同で生み出す
13 【教育と教育組織】
フランスの DH―スタンダール大学における教育と研究―●長野壮一
1.グルノーブルにおけるDH教育/2.グルノーブルにおけるDH研究(1):「グルノーブル第2・第3大学デジタル図書館」/3.グルノーブルにおけるDH研究(2):「スタンダール手稿」/4.グルノーブルにおけるDH研究(3):「Fonte Gaia」/5.おわりに
14 【人材とキャリアと教育】
イベントレポート Digital Humanities 2018 ●鈴木親彦
1.人材とキャリア/2.人文情報学は基礎教育にどうかかわるか/3.未来の研究者を育てるという観点
15 【大学院生のフェロープログラム】
カロライナ・デジタル・ヒューマニティーズ・イニシアティブ・大学院生フェローの経験を通じて●山中美潮
1.はじめに/2.Digital Innovation Lab (DIL)(2-1.概要/2-2.マッピング)/3.CDHIとは(3-1.概要/3-2.大学院生フェロー・プログラム/3-3.講義)/4.個人プロジェクト:“The Fillmore Boys School in 1877”(4-1.プロジェクトの背景/4-2.データ作成/4-3.ArcGISによる地図作成/4-4.ウェブサイト作成/4-5.成果と反省)/5.UNCにおけるデジタル・ヒューマニティーズの現在/6.おわりに
第2部 時代から知る
序 古代●小川 潤
1.デジタル技術を活用した古代研究への関心と評価/2.「データの構築・整備」「データの共有・公開」の二つの論点/3.具体化できる四つの要素/4.幅広い情報共有や教育活動/5.未来に向けての手掛かりに
1 【英国の墓碑情報をどうマークアップするか】
イベントレポート Digital Classicists / ICS Work-in-progress seminar●髙橋亮介
1.古代ギリシア・ローマ研究のデジタル・ヒューマニティーズのセミナー/2.方法論や研究システムの構築/3.墓碑の情報をEpiDocでマークアップする
2 【人文情報学の先駆的電子図書館】
Perseus Digital Library●吉川 斉
1.Perseusプロジェクトの歴史/2.Perseusでホメロス『イリアス』を読む(2-1.準備/2-2.本文を読む)/3.Perseusの電子化データ
3 【西洋の古典文学叢書の電子版】
The digital Loeb Classical Library●吉川 斉
1.基本編:DLCLを操作する(1-1.作品を探す/1-2.作品を読む/1-3.本文を検索する)/2.発展編:DLCLを購読して利用する(2-1.DLCLの購読手続き/2-2.プロファイルを作る(ログイン/サインイン)/2-3.ログインして使ってみる)/3.DLCLの電子化の在り方について
4 【これまで存在しなかったシステムを構築する】
Perseus Digital Libraryのプロジェクトリーダー Gregory Crane氏インタビュー●小川 潤
1.ペルセウスをどう始めたか/2.コンピューター科学と人文学の垣根が低いドイツ/3.ペルセウスの現在/4.ペルセウスと他の資料/5.校訂版をどう作るのか/利用と引用/6.これまで存在しなかったシステムを構築する
5 【紙媒体の校訂記号をデジタル校訂に利用する】
西洋古典・古代史史料のデジタル校訂とLeiden+―デジタル校訂実践の裾野拡大の可能性―●小川 潤
1.紙媒体の校訂記号をデジタルでも利用/2.Leiden+とは何か/3.文構造/4.テクスト校訂/5.異読等の注釈/6.Papyri.infoでの利用法
6 【形態・統語情報をテキストに付与する】
Arethusa による古典語の言語学的アノテーション―構文構造の可視化と広範なデータ利活用の実現―●小川 潤
1.二つの目標/2.アノテーションを付与する方法/3.自動的にXML で記述/4.教育への利用可能性
7 【ギリシア語のコーパス】
PapyGreekによる歴史言語研究のためのギリシア語コーパス構築の試み―文書パピルスの言語学的アノテーション―●小川 潤
1.ギリシア語コーパスPapyGreek/2.操作方法/3.アノテーション/4.ビッグデータに基づいた歴史言語学的研究に寄与
序 中世●纓田宗紀
1.歴史基礎学を介して中世学に浸透したDH/2.手書き文字の読解のためのさまざまな取り組み/3.中世テクストのデジタルデータ作成とその教育方法/4.日本の西洋学者は何をやっているか
1 【画像情報とデジタル・ヒューマニティーズの可能性】
デジタル技術を用いた古書体学―シンポジウム参加報告―●永井正勝
1.はじめに/2.コンピュターを利用した人文学研究の拠点を目指す組織、DigiPalの来歴/3.シンポジウムのプログラム/4.発表内容/5.文書のデジタル画像化とその活用、メタデータ/6.メタデータの作成とTEI/7.情報工学からのアプローチ/8.「古書学研究における確証的にして便利なツールとは何か」/9.画像情報を用いたDHの可能性
2 【難読箇所読解のウェブシステム】
中世写本のラテン語の難読箇所を解決するEnigma●赤江雄一
1.このツールを必要とする人は/2.「難読箇所」とはどこか/3.可能性のある語彙がリストアップされる/4.実際に使ってみて/5.使いこなすコツ/6.人文学の研究に関わり続けることの重要性
3 【史料批判の精度を高めるためのTEI】
リヨン高等師範学校講義「中世手稿のデジタル編集」参加記●長野壮一
1.初日/2.2日目/3.3日目/4.4日目/5.5日目/6.DH教育プログラムの中世研究における意義
4 【分野横断的基軸としてのデジタル人文学】
フランスのDH―リヨンCIHAMを中心として―●長野壮一
1.デジタルツール(1-1.Enigma/1-2.Interactive Album of Mediaeval Palaeography/1-3.TEI Critical Apparatus Toolbox/1-4.Correcteur Orthographique de Latin)/2.史料コーパス (2-1.Sermones latins/2-2.Ressources comptables en Dauphiné, Provence, Savoie et Venaissin (XIIIe-XVe siècle))
5 【デジタル技術を使って新しい問いを立てる】
ヨーロッパの初期印刷本とデジタル技術のこれから●安形麻理
1.英米流の書誌学とシェイクスピア研究/2.西洋の初期印刷本のテキストデータ/3.デジタル技術を用いた初期印刷本の研究/4.高品質のデータと研究者の役割
6 【書物史の新たな知見を広げる】
インキュナブラ研究とcopy-specific information●徳永聡子
1.同じ版の本でも、同じ本は一冊もない/2.インターネット公開が主流となった目録/3.横断検索と数量分析、可視化
7 【元データがAPIとXMLファイルで提供される目録】
Regesta Imperii Online の活用●纓田宗紀
1.はじめに/2.RIプロジェクト/3.RI Online/4.データの活用例:教皇特使研究への適用/5.おわりに
序 近世●長野壮一
1.近世研究におけるの浸透/2.近世研究におけるデジタル技術援用の背景/3.DHが近世研究にもたらす影響
1 【シェイクスピア研究】
デジタルなシェイクスピアリアンの1日●北村紗衣
2 【デジタル英文学研究を考える】
イベントレポート 第53回シェイクスピア学会セミナー―Digital Humanities and the Future of Renaissance Studies―●北村紗衣
1.はじめに/2.日本ではなじみの薄いデジタル英文学研究/3.EEBO-TCP─フルテキストサーチ機能がついたDB/4.過去のパフォーマンス空間を再現するプロジェクト/5.超えなければならない壁
3 【ボドリアン図書館所蔵ファースト・フォリオプロジェクト】
JADH2015特別レポート『御一統の温かいことばあってこそわが帆ははらむ。さなくばわが試みは挫折あるのみ』─ボドリアン・ファースト・フォリオの来歴について ●Pip Willcox(長野壮一・永﨑研宣訳)
1.はじめに/2.ボドリアン図書館所蔵ファースト・フォリオの来歴/3.シェイクスピアへの全力疾走/4.ボドリアン・ファースト・フォリオ/5.助言と願望/6.実現と共同作業/7.目下の作業/8.今後の作業/9.私自身について
4 【全出版物調査をどう行うか】
三大デジタルアーカイブのデータセット比較と近世全出版物調査プロジェクト●菊池信彦
1.はじめに/2.記事概要/3.結論から感じた疑問/4.Iberian Booksプロジェクト
5 【「シェイクスピア」とは何で「デジタル」とは何か】
書評 “Shakespeare and the Digital World: Redefining Scholarship and Practice”●北村紗衣
6 【メタデータの視点からデータベースを考える】
発表レポート 17世紀アイルランド史個別事例研究 “Utilising 1641 Depositions in History: A Statistical Study”●槙野 翔
1.はじめに/2.報告要旨/3.データベース紹介/4.データ取得・可視化/5.振り返り・問題点/6.おわりに
7 【マッピングとネットワーク分析】
18世紀研究におけるDHの広がり 第1回 個別発表にみるデータの可視化―第15回国際十八世紀学会(ISECS 2019)に参加して―●小風綾乃
1.はじめに:国際十八世紀学会について/2.マッピング/3.ネットワーク分析/4.おわりに
8 【印刷史料・議会記録のウェブコンテンツ】
18世紀研究におけるDHの広がり 第2回 各種ウェブコンテンツの紹介(1)―第15回国際十八世紀学会(ISECS 2019)に参加して―●小風綾乃
1.はじめに/2.18世紀研究に役立つウェブコンテンツ(2-1.出版物を対象とした広範な検索ポータル:ESTC, Le gazetier universel/2-2.特定の刊行物を対象としたデジタル校訂版テキスト:DIGITARIUM, MHARS, Philosophie cl@ndestine, ARTFL, ENCCRE/2-3.特定の時期・ジャ
内容紹介
デジタル技術と人文学の新たな関係が求められているいま、押さえておきたい思想と技術が学べる本。
西洋世界におけるデジタル・ヒューマニティーズの研究・教育の主流を形成しているのは欧米圏の組織やプロジェクトが多いが、言語の壁や情報技術の進歩の速さのため、あるいは西洋研究の文脈での知識が必要であるといった事情から、日本で西洋世界のデジタル・ヒューマニティーズに関する情報を入手するための手だてはいまだ乏しい。この問題意識のもと、メールマガジン『人文情報学月報』に掲載された記事を加筆・修正する形で、西洋世界におけるデジタル・ヒューマニティーズの研究・教育の成果を知る本を編みました。
第一部では哲学から教育まで、テーマ別にデジタル・ヒューマニティーズを把握できるよう配列。第2部は「時代から知る」と題し、古代から近現代までを研究対象としたさまざまな実践を紹介。第三部は宮川創氏によりドイツ・ゲッティンゲン大学を中心とした欧州各地での事例を紹介します。
執筆は、小風尚樹/小川潤/纓田宗紀/長野壮一/山中美潮/宮川創/大向一輝/永崎研宣/Neil Fraistat/菊池信彦/横山説子/Alex Gil/Niall O’Leary/西川開/James Cummings/鈴木親彦/髙橋亮介/吉川斉/永井正勝/赤江雄一/安形麻理/徳永聡子/北村紗衣/Pip Willcox/槙野翔/小風綾乃/松下聖/舩田佐央子の各氏。
【本書が目指すのは、西洋世界を題材として扱うDHの研究動向を調査するための足がかりを提供することである。本来、最新の学界動向を追えることが理想的ではあるが、その情報のみをピンポイントで知ることは容易でない上に、それだけを知っても効果的にそれを活用することは難しい。本書はあくまでも点描にすぎないものの、それを通じて全体の雰囲気をつかむと同時に、類例を介して関心ある分野における状況を調査するための土台を築く手助けとなることを、編者としては願っている。】序より。
著者について
一般財団法人人文情報学研究所 (イッパンザイダンホウジンジンブンジョウホウガクケンキュウジョ)
2010年、SAT大蔵経テキストデータベースの運用を支援しつつ、これを基礎とする仏教学のためのデジタル研究環境構築を目指し、人文情報学的知見を開発して人文知の宝庫である仏教の研究を推進し、さらに、これをとおして人文学全体を振興するとともに、広く人類精神文化の発展に寄与する目的をもって設立された研究所。仏教経典研究部門、仏教写本研究部門、人文情報学研究部門の三部門を擁する。これらの各部門における研究活動に加えて、2011年より月刊の無料メールマガジン『人文情報学月報』を発行し、日本デジタル・ヒューマニティーズ学会の事務局を引き受ける等、人文情報学に関わる情報共有と連携を重点事項の一つと位置づけて取り組みを続けている。ハンブルク大学、国文学研究資料館等と連携協定を結んでいる。
東京都文京区本郷5-26-4-11F TEL:03-6801-8411 FAX:03-6801-8412
https://www.dhii.jp/
小風 尚樹 (コカゼ ナオキ)
1989年生まれ。千葉大学助教。東京大学人文社会系研究科西洋史学専門分野博士課程在籍、キングス・カレッジ・ロンドンデジタル・ヒューマニティーズ修士課程首席修了。修士(東京大学・文学)、Master of Arts(King’s College London, Digital Humanities)。国立歴史民俗博物館RA、東京大学史料編纂所特任研究員等を経て現職。学会関連活動として、日本デジタル・ヒューマニティーズ学会「人文学のための情報リテラシー」研究会主査、東アジアブリテン史学会委員、Tokyo Digital History代表等がある。論文に、「イギリス海軍における節約と旧式艦の処分:クリミア戦争からワシントン海軍軍縮条約を中心に」(『国際武器移転史』第8号、2019年)、「アトリエに吹く風:デジタル・ヒストリーと史料」(共著、『西洋史学』第268号、2019年)、‘Toward a Model for Marking up Non-SI Units and Measurement’ (筆頭著者、Journal of Text Encoding Initiative, Iss…
小川 潤 (オガワ ジュン)
1994年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程。修士(東京大学・文学)。論文に、「帝政初期ローマ皇帝によるガリア統治政策とドルイド弾圧再考:皇帝属州ガリアにおけるローマ化の一側面」(『クリオ』第32号、2018年)、「歴史研究における社会ネットワーク分析の活用と可能性:古代史研究における人的ネットワーク分析を事例に」(『西洋史学』第269号、2020年)など。
纓田 宗紀 (オダ ソウキ)
1989年生まれ。アーヘン工科大学博士候補生、ゲルダ・ヘンケル財団奨学生。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。修士(東京大学・文学)。論文に、「1059年の教皇選挙令と枢機卿団の形成」(『クリオ』第28号、2014年)、「アトリエに吹く風:デジタル・ヒストリーと史料」(共著、『西洋史学』第268号、2019年)など。
長野 壮一 (ナガノ ソウイチ)
1988年生まれ。社会科学高等研究院(EHESS)博士課程、千葉大学特任研究員。 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程中途退学。修士(東京大学・文学)。論文に「デジタル歴史学の最新動向:フランス語圏におけるアーカイブ構築およびコミュニティ形成の事例紹介」(『現代史研究』第61号、2015年)、「団結と結社:フランス刑法典第414~416条改正の概念史的考察 (1862~1864年) 」(『史学雑誌』第126編第12号、2017年)、共著に『歴史を射つ』(御茶の水書房、2015年)など。
山中 美潮 (ヤマナカ ミシオ)
1986年生まれ。同志社大学アメリカ研究所助教(有期)・専任研究員。ノースカロライナ大学チャペルヒル校博士課程修了。Ph.D.(history)。南山大学非常勤講師等を経て現職。主要論文に「アメリカ史研究とデジタル・ヒストリー」(『立教アメリカン・スタディーズ』第40号、2018年)、“African American Women and Desegregated Streetcars: Gender and Race Relations in Postbellum New Orleans”(Nanzan Review of American Studies 第40号、2018年)、「2019年の歴史学会-回顧と展望-アメリカ(北アメリカ)」(分担執筆、『史学雑誌』第129編、第5号、2020年)など。
宮川 創 (ミヤガワ ソウ)
1989年生まれ。京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター助教・情報ネットワーク管理室助教兼任。京都大学大学院文学研究科言語学専修博士後期課程研究指導認定退学。ゲッティンゲン大学エジプト学コプト学専修博士課程。修士(京都大学・文学)。ドイツ研究振興協会特別研究領域研究員、関西大学アジア・オープン・リサーチセンターPDを経て現職。論文に、「コプト教父・アトリペのシェヌーテによる古代のコプト語訳聖書からの引用」(『東方キリスト教世界研究』第5号、2021年)、「ローマ・ビザンツ期エジプトのデジタルヒストリー : コプト語著述家・アトリペのシェヌーテを中心に」(『西洋史学』第270号、2020年)、‘Optical Character Recognition of Typeset Coptic Text with Neural Networks’(筆頭著者、Digital Scholarship in the Humanities 34, Suppl. 1、2019年)など。
大向 一輝 (オオムカイ イッキ)
1977年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。著書に『ウェブがわかる本』(岩波書店、2007年)、『ウェブらしさを考える本』(丸善出版、2012年、共著)、論文に「オープンサイエンスと研究データ共有」(『心理学評論』61-1、2018年)など。
永崎 研宣 (ナガサキ キヨノリ)
1971年生まれ。一般財団法人人文情報学研究所主席研究員。筑波大学大学院博士課程哲学・思想研究科単位取得退学。博士(関西大学・文化交渉学)。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所COE研究員、山口県立大学国際文化学部助教授等を経て一般財団法人人文情報学研究所の設立に参画。これまで各地の大学研究機関で文化資料のデジタル化と応用についての研究支援活動を行ってきた。学会関連活動としては、情報処理学会論文誌編集委員、日本印度学仏教学会常務委員情報担当、日本デジタル・ヒューマニティーズ学会議長、TEI Consortium理事等がある。著書に『文科系のための情報発信リテラシー』(東京電機大学出版局、2004年)、『日本の文化をデジタル世界に伝える』(樹村房、2019年)など。